「お問い合わせ」はお気軽に
親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など
「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています
体験予約・個別相談は
03-6265-0446
平日10時~18時
相談してみる
「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の
お試しのため来店を希望される場合は
原則ご予約をお願いします。
※予告なくお休みとなる場合があります。



画像はイメージです

雑誌、Web広告などを中心に幅広く活動中。現在、80代の母親と同居するリアル「オヤノコト」世代。聴こえの衰えや唐突に前後する会話に母親の“年齢”を実感しつつも「まだまだ元気そうだし…」と、趣味である野球観戦やライブ遠征に備え、食べるための「歯」・元気で過ごすための「足」の健康維持に励む日々。
きこえの衰えによって「高齢の親との会話がスムーズにできなくなってきたけど、補聴器を使うほどではないかな」と思っていませんか? でもその“放置”が大きな後悔になる可能性があるとしたら――少しでも早くきこえ対策を考えるべき「本当の」理由をお伺いしました。
●お話をお聞きした人
WSオーディオロジージャパン株式会社 成井あい子さん。 同社が運営する「難聴と補聴器のポータルサイト、きこえナビ」運営ご担当。 補聴器販売店のマーケティングを5年間、補聴器メーカーのマーケティングを6年間ご担当。高齢の親のため、私たち「オヤノコト」世代のために、よりよいきこえと補聴器についての情報を発信されています。
我が家は80代の実母を含めた家族暮らし。足腰や認知の問題もなく、毎日元気に過ごしている母ですが、数年前から「きこえの衰え」が顕著に。今では会話中に何度も聞き直しされる、大声で何度も言い直さないと聞き取ってもらえない状態となっており、仕方ないこととはいえ、私たち姉妹はどうしてもイライラしてしまう場面が増えています。

さすがにこの状態はマズイと、今、補聴器の使用を検討しているのですが、心配なのは、ここまできこえが衰えた母が補聴器を使うことで「どのくらいきこえが回復するのか」ということ。補聴器を使えば、もっとスムーズな会話ができるようになるのでしょうか。
「お話をお伺いした限りでは……正直、対策がかなり遅いなという印象ですね」
と、語るのは、WSオーディオロジージャパン株式会社が運営する「難聴と補聴器のポータルサイト、きこえナビ」の運営をご担当されている成井あい子さん。
「音をきくというのは皆さん『耳』がやることだと思っていると思いますが、耳の役割は音を集めることと伝えることです。入ってきた音を分析して、何と言っているのかを理解するという役割は『脳』が担っています。難聴になって、耳から入る音刺激が少なくなると、この『入ってきた音を分析して理解する』働きが衰えるので、音はきこえても、それを理解できないという状況になってしまうのです」(成井さん/以下同)

「例えば、補聴器を使用することで、耳から多くの音刺激が入ってくるようになったとしても、その音を分析し、理解するために必要な脳の機能が一緒に復活するわけではありません。もう一度いろんな音を聞いて、音を理解する学習をし直すことが必要であり、それは聞こえなかった期間が長ければ長いほど時間がかかりますし、結局以前と同じようには回復しない可能性もある。せっかく補聴器を使っても『音はきこえるけれど、何を言っているのかわからない時もある』という意見があるのは、こうした理由によるものと考えています」
我が家もそうですが……たぶん、ほとんどの方が『会話が成立しなくなってきたから、補聴器を使おう』と考えるのではないかと思います。でも、それではせっかくの補聴器の機能を最大限に活かしきれない可能性もあるということ。きこえの対策は、私たちが今まで考えていたタイミングよりもだいぶ早い段階から始めておくべきなのです。
参考:『きこえナビ』家族が難聴かも?4つの兆候と今すぐ家族がしてあげるべきコト(外部サイトに飛びます)
では、補聴器をつけた時に、その機能を最大に活かすことができる、装着したら、コミュニケーションが改善する……ということを目標とするならば、どのような自覚症状を感じた段階で導入を検討すべきなのでしょうか。
「やはり一番具体的なのは、耳鼻科で聴力検査を受けて、その結果で判断するという方法だと思います。難聴の度合いは軽度・中等度・高度・重度の4段階に分かれていますが、人によっては軽度、少なくとも中等度になったら使い始めたほうが、利用される本人も違和感なく使えてとても楽なのではないかと思います」
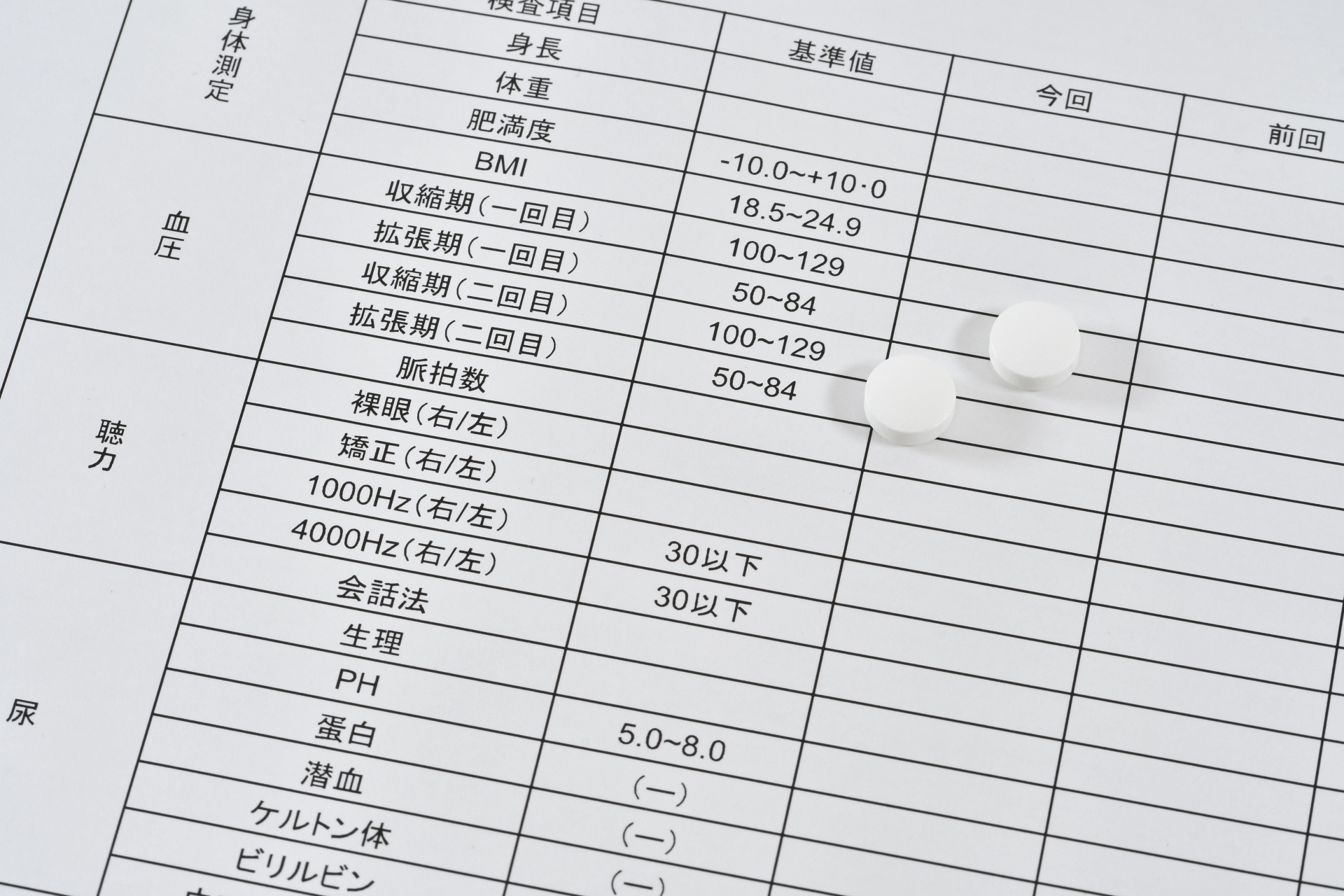
我が家の母も、補聴器を作ろうと考え、先日耳鼻科で聴力検査を受けましたが、そこでの診断は中等度から高度難聴という結果でした。成井さんのお話に照らし合わせると、これはできるだけ早めに補聴器を使った方がいいレベルだと思うのですが……検査後の診断では「使った方が便利だと思うよ」といった、軽い感じ(?)のアドバイスだったこと、また「全く音が聞こえないわけではない」という状態もあって、私も母親もそこまで深刻に考えることなく、結構のんびり構えてしまっていたところがあります。
でもそこがきこえの対策を後回しにしてしまう、大きな要因になってしまっているのだとか。
「例えば視力が落ちると、目に入ってくるものが一律に見えにくくなりますよね。だから視力が落ちたことも自覚しやすいですし、『不便だから眼鏡を作ろう』となります。でも聴力は全ての音が一律にきこえなくなるわけではありません。鳥の声や車が走る音、家電製品のアラームといった一部の音から徐々に聞こえなくなっていく。会話やテレビの音は、聞き間違いが多いとしても、理解できる程度にはきこえているので、きこえが衰えていることに気づかないことが多く、家族やお友達に指摘されても『そんなことない!』と否定される方もいらっしゃいます」

きこえが衰えることによって、音がどうきこえるようになるのか――それは本当に人それぞれ。アラーム音など特定の音からきこえなくなる場合もあれば、例えば「しゃべっている」という単語の最初の「し」だけが聞き取れないなど、音が欠けたようにきこえなくなる場合も。それでも普通に音は耳から入ってくるため、「会話の内容がわからなくて不便」と本人が自覚したときには、すでに、きこえの状態が悪化していることが少なくないのです。
「とはいえ、補聴器の使用に『遅すぎる』というタイミングはないと思っています。検査したら難聴の度合いも高度になっていて、会話もスムーズにできないという状態であっても、補聴器を使うことで少なくともある程度は改善させることはできるでしょう。ですが、大切なのはとにかくすぐに対処すること。きこえの衰えを感じたら、すぐに耳鼻咽喉科を受信し、難聴ということであれば、すぐに補聴器販売店に相談してみましょう」
我が家の母にきこえの衰えが見え始めたのは、実はもう10年も前のこと。「会話中に聞き直しされる回数が増えた」、加藤さんと佐藤さんなど「名前や言葉の聞き間違いが見られるようになった」といった程度でした(「子音_カ・サ・タ」が聞こえにくくなるそうです)。それが数年で一気に加速、気づいた時には普通の声量では会話中に何度も聞き返しされるまでになっていました。

ここまで成井さんのお話をお伺いする限り、わが家の場合は完全に「母のきこえを放置しすぎた」状態であり、その点はもう少し気を遣うべきだったと反省しています。でも、今、専門医に行ったり、補聴器専門店を探したりしているのは、母自身がきこえに不便を感じ「補聴器を作ろうかな」と言い出したからであり、もし母がそれを言い出さなかったら、たぶん「まだ大丈夫だろう」ともっと放置していただろうなとも思います。
ではもし、このまま母のきこえの衰えを放置し続けていったとしたら――どんなトラブル、デメリットが起こる可能性があるのでしょう。
「やはり認知機能が低下するリスクが高まることだと思います。難聴になると認知症になるリスクが高くなるということは政府からも発表されています。もちろん『難聴になる=絶対に認知症を発症する』というわけではありませんが、認知症を引き起こす危険因子の調査によると、危険因子の中で対策可能なもののうち、一番リスクが高いとされているのが難聴なのです。このような調査結果がある以上、難聴になったら早めにケアするようよびかけていくべきだと考えています」

認知症になると、発症した本人はもちろん、その家族も辛く、その後、さまざまな負担が生じる恐れがあります。そしてその期間が長ければ、「オヤノコト」世代の仕事や家庭、生活の形を大きく変えてしまう可能性もあります。きこえの衰えを放置することが、その大きな要因になるとわかっているのであれば……高齢の親にとっても、家族にとってもそれを放置しておいてよいことは何一つありませんよね。
「きこえが衰えてきたけどどうしよう……と放置したら状態が悪くなることはあっても、良くなることはほぼありません。どこでケアを始めるか、そのタイミングはそれぞれの判断にはなりますが、難聴の度合いが進んでから補聴器をつけてもスムーズに使いこなすまでにはかなりの時間がかりますから、やはり、できる限り早めの対策を考えたほうが、その後の生活もかなり変わってくるのではないでしょうか」
参考:『きこえナビ』難聴を放置しない! 家族を説得する方法と補聴器以外の対応策の3つのポイント
(外部サイトに飛びます)
・・・いかがでしょうか。
ここまで高齢の親の「きこえの衰え」と、早めに対策・ケアをすることの重要性についてご紹介しました。今回、成井さんのお話しを聞いて、今度、早い段階にわが家も補聴器専門店に相談に行こうと思っています。
そこで次回は、実際に「補聴器を作ろう」となった時にやるべきこと、どこで、どんな補聴器を作ればいいのかなどの「選び方」についてご紹介します。他人事ではない、高齢の親のきこえ問題、これからの対策、補聴器購入などいっしょに考えていきましょう。
(取材:2025年8月)
調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら