「お問い合わせ」はお気軽に
親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など
「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています
体験予約・個別相談は
03-6265-0446
平日10時~18時
相談してみる
「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の
お試しのため来店を希望される場合は
原則ご予約をお願いします。
※予告なくお休みとなる場合があります。



©️「104歳、哲代さんのひとり暮らし」製作委員会
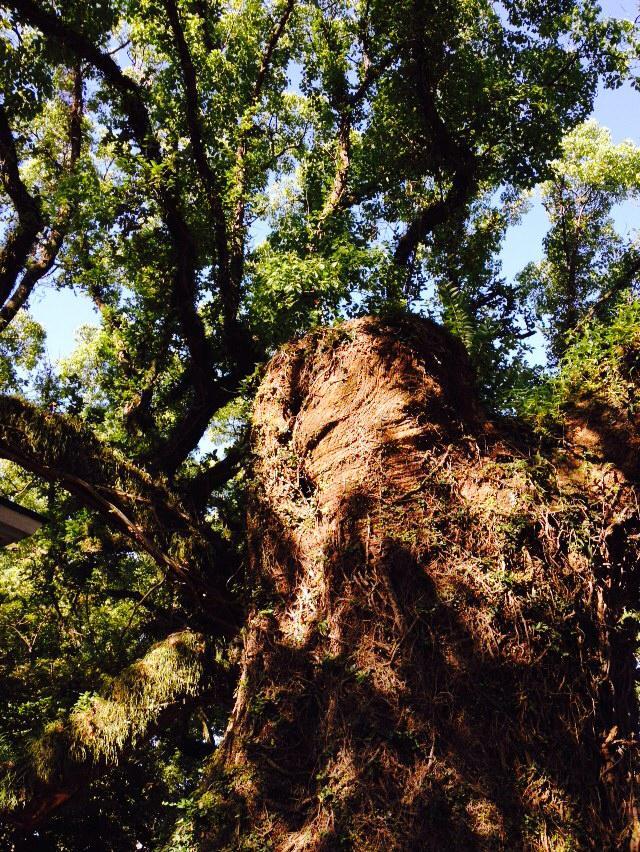
20年ほど前に親を呼び寄せ、母を看取った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて考えるように。施設やそこで暮らす親世代、認知症、高齢の親と子どもの関係、終末期に関するブックレビューなどを執筆
「センテナリアン」という言葉をご存じでしょうか。100歳を超えた長寿者のことをこう呼ぶそうです。日本語だと百寿者ですね。厚生労働省による住民基本台帳に基づいた資料では、2024年で95,119人もいるとのこと。そのうち女性が9割近くを占めています。
さらに100歳を超えて介護が必要でない人となると、もっと絞られます。厚生労働省の「令和5年度介護給付費等実態統計」によれば、年齢別、人口に占める受給者数の割合は、95歳以上で男性が69.2%、女性が86.6%(さすがに100歳以上のデータはありませんね)。つまり95歳を超えて自立した生活ができているのは、女性だと1割強しかいないということになります。
そんな“特別”な人ってどんな人? と、さまざまなメディアが「センテナリアン」を取り上げています。100歳を超えても自立して暮らすだけでなく、医師とか薬剤師、理美容師などとして活躍する人やマスターズに出場する人など……。その姿を見て、「自分もまだまだがんばらなくては」と鼓舞される親世代や子世代は多いのではないでしょうか。
いまや人生100年時代。とはいえ、「自分がその齢まではとても元気でいられるとは思えない」「やはり選ばれた人たちなのだ」と諦めの境地にもなる人もまた少なくないと思います。
その“特別な”人のひとり、101歳の地質学者 杉村新さんは、長生きの秘訣を聞かれて「確率」と答えたのだそうです。それを聞いた東大地震研究所の岩森光教授は、「この答えに科学者の真骨頂をみる思いがした」と言っています。「確率」、つまり「病気になるリスクも遺伝的な背景もすべて確率的な現象なのだ」という杉村さんの言葉に、少し気が楽になりました。「長生きの秘訣」なるものがあったとしても、同じように実行している人が必ずしも長寿とは限りません。やはり結局は「確率」なのです。
今回ご紹介する映画「104歳、哲代さんのひとり暮らし」の主人公、広島県尾道市でひとり暮らしをする石井哲代さんも「確率」のなかの一人です。102歳、103歳のときに著書を出版するなど、その暮らし方や含蓄ある言葉が注目を浴びています。
ちなみに広島にはもうひとり、有名な「センテナリアン」がいます。映画「ぼけますから、よろしくお願いします」に登場した、呉市に住む信友良則さん。哲代さんと同じ104歳で、二人はすでに対談済みです。なんたる最強タッグでしょうか。
さて、その哲代さんのひとり暮らしを描いた映画を見ながら感じたのは、哲代さんは確かに“特別”な人ではあるのですが、現実は想像していたのとは少し違うということです。

映画は、足を痛めて入院していた哲代さんが、退院して自宅に戻った日からはじまります。自宅前の長い坂道を、そろそろと後ろ向きに下りて行く姿は、まさに哲代さんの今を象徴しているようでした。緩やかに坂を下っていく哲代さんの、101歳から104歳の姿を――。
料理中にエプロンや髪を焦がして電磁調理器に変えたり、足の炎症で再び入院したあとは、姪の家に滞在してリハビリをしたりと、ありのままの老いの現実も見せてくれます。103歳でひとり暮らしを再開すると、さすがにヘルパーの手を借りることになったのです。
春日キスヨさんは、著書『百まで生きる覚悟』(光文社)のなかで、こうした状態を「『ヨロヨロ』と生き、『ドタリ』と倒れ、誰かの世話になって生き続ける」と書きました。92歳の樋口恵子さんは「ヨタヘロ期」と称しています。どれほど“特別”なセンテナリアンでも、それは免れないということなのでしょう。普通の人よりは20年から30年ほど遅いというだけで。いや、それでも十分にすごいことなのですが。

一方で、哲代さんは104歳とは思えないほど活発に行動しています。自らが立ち上げた地域の高齢者の集まり「仲よしクラブ」に参加し、施設に入っている妹を神戸まで見舞い、米寿を迎えた教え子(というのも驚きです)から招かれて同窓会に出席する……これもまた、タフな哲代さんの日常なのです。
小学校教員としてたくさんの教え子を世に送り出し、退職後は民生委員として地域に貢献してきた哲代さんですが、本家の嫁として、子どもを産めなかったことを今もなお「負い目に感じている」という切ないシーンもありました。

それでも哲代さんは一人ではありません。姪たちや地域の人が哲代さんのひとり暮らしを助け、支えています。それは、これまで哲代さんが築いてきた人間関係のたまものなのでしょう。まさに、国が目指す「住み慣れた地域で、その人らしい暮らしを人生の最期まで続ける」という地域包括ケアの理想の姿がありました。
その後も老いの坂道は続きます。哲代さんは、103歳の秋に三たび足の状態が悪化して入院、施設への入居も考えるように。そして104歳の春は――。
「●歳の壁」が流行語になり、「壁」を乗り越える努力をしている人は少なくないと思います。この映画で、「壁」の乗り越え方や長生きの秘訣、さらには高齢になっても自立して暮らすコツを知りたいと思うのなら、「これかな」というポイントは確かに見つかるでしょう。でも、哲代さんが教えてくれるのはそれだけではありません。決して“特別”なだけではない。100年以上生きて、悩みも苦しみも哀しみも、私たちと同じように、いえ私たち以上に味わってきたのだということ。もちろん、喜びも。
105歳の哲代さんにもまた会いたい!
◆『104歳、哲代さんのひとり暮らし』
ナレーション:リリー・フランキー 監督・編集:⼭本和宏 撮影:的場泰平 筒井俊⾏ ⾳響効果:⾦⽥智⼦ 整⾳:富永憲⼀ プロデューサー:中村知喜 古⽥直⼦ 出雲志帆 髙⼭英幸 統括プロデューサー:岡本幸
制作:RCC 協⼒:RCCフロンティア 公益財団法⼈ ⺠間放送教育協会 中国新聞社
後援:広島県 尾道市 府中市
配給:リガード
2024/⽇本/94 分/ドキュメンタリー/©「104 歳、哲代さんのひとり暮らし」製作委員会
2025年1⽉31⽇(金)より広島先⾏公開中 4⽉18日(金)よりシネスイッチ銀座ほか全国順次
調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら