「お問い合わせ」はお気軽に
親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など
「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています
体験予約・個別相談は
03-6265-0446
平日10時~18時
相談してみる
「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の
お試しのため来店を希望される場合は
原則ご予約をお願いします。
※予告なくお休みとなる場合があります。


第3回:ご相談者60代 対象者(母親)90代


20年ほど前に親を呼び寄せ、母を看取った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて考えるように。施設やそこで暮らす親世代、認知症、高齢の親と子どもの関係、終末期に関するブックレビューなどを執筆
前回に続き、「オヤノコト」®相談室に来られた大塚さんの体験をご紹介しています。大塚さんの母親は認知症ながらも穏やかに暮らしていたのですが、不穏な行動がみられるようになり、突然夜中に叫んで暴れ出しました。大塚さんの虐待を疑ったケアマネジャーからショートステイを提案されましたが、たった2日間のショートステイで母親の状態はさらに悪化、救急病院に搬送されてしまいます。歩くこともしゃべることもできなくなった母親を自宅に連れ帰ることもできず、転院先を何とか見つけてもらったのですが……。
この転院先も十分なケアをしてくれなかったと大塚さんは憤慨します。
「職員からは、母が拘束されていると聞きました。コロナで面会もできず、母の様子もわからない。こんなところにずっといたら、もっと悪化してしまうのは目に見えています」
大塚さんが知り合いに相談したところ、隣の市の認知症専門病院を紹介され転院させてもらえることになりました。新しい病院に着くまでの間、介護タクシーの中で大塚さんと弟が母親に話しかけていると、だんだん言葉が戻ってきて大塚さんを安心させました。「やはり家族が近くにいないとダメだ」と改めて実感したのです。
転院した病院で母親は身体拘束をされることもなく、増えていた投薬量も大幅に減らすことができました。そして、ここではじめて母親はレビー小体型認知症と診断されたのです。レビー小体型認知症とは、高齢期に認知症を呈する病気のひとつで、特徴的な症状が幻視や幻聴などの幻覚です。これで、大塚さんはなぜ母親があの夜せん妄を起こしたのか腑に落ちたと言います。
「それにしても、これまでに受診した病院の診断は何だったのでしょうか。どこかで適切な診断をされていれば、母もここまでひどい状態にならなくて済んだのに」
ところがリハビリも開始したと聞き、希望が見えてきたのもつかの間、次第にこの病院にも不信感が募るようになったのです。
コロナ禍で、母親とは数か月会えなくなっていました。母親の状態を知りたくても、担当医からは何の説明もないと言います。そのうえ、入院費のうち実費として毎月多額の請求が来るのにも納得できません。
「一番わからないのが、『入院セット』という名目の費用です。それが1日約2000円、月に6万円近くの請求が来るんです。内訳の記載もないので、何のお金かも、その単価もわかりません。タオルやパジャマ、肌着は母のものを持って行っていますし、洗濯代だけでこんなにかかるはずがありません」
調べてみると、入院セットは病院とは別会社と契約していることになっていました。病院を通して、その会社に何度も説明を求めましたが回答はありませんでした。
大塚さんが、このままでは母親の状態がさらに悪化してしまうと、有料老人ホームに移そうと考え、「オヤノコト」®相談室に来られたのは、病院への不信が極限に達したころでした。
母親が今どうなっているのか不安が募っていたので、なるべく早く転居させたいと思っていた大塚さん。ホーム探しにかけられる時間は多くありませんでした。何か所かのホームの担当者が、母親を受け入れられるか判断するために病院に行って状況を聞いたところ、驚く事実が判明したのです。
「母は口から食事が摂れず、水分を補給するための点滴で命をつないでいるということでした。面会もできず、医師からの説明もないまま、母はそんな状態になっていたんです。そして何より衝撃だったのは、背中に大きな褥瘡(じょくそう)ができているというのです」
もちろんこれまで病院からは何の報告もありませんでした。有料老人ホームへの転居を見据えて、ホームの担当者が病院に行って話を聞いてくれて初めて、「実は褥瘡(じょくそう)ができている」と伝えられたのです。
「その褥瘡(じょくそう)は、ホームの担当者も目を覆うほどひどいものだったそうで、言葉を失いました。ホームに転居することを決めなければ、隠したまま放置されていたのでしょう……」
この病院でさらに認知症が進んだ母親は、褥瘡による痛みを訴えることもできなかったのでしょう。どんなに痛かったことか。大塚さんはもっと早く転居を検討しなかったことを悔やみました。
皮肉なことに、母親の栄養補給方法や褥瘡(じょくそう)が壁となって、ホーム探しは難航しました。「お母さまの状態を考えると、うちでは引き受けることができない」と、複数のホームに断られたのです。
最終的に「引き受け可能」という返事がもらえたのは、大塚さんの自宅に近いKホームからだけでした。
「Kホームは褥瘡(じょくそう)のひどい母親のためにウォーターベッドを取り入れましょうと提案してくれました。さらに職員が母を車いすに乗せて、近くの公園に連れて行く計画までしてくださったんです。母がもう外に出られることはないだろうと諦めていたので、ただ感謝するばかりです」
そして、Kホームに移って2週間。母親は静かに旅立ちました。
「それでも、母が最期にこのホームで過ごすことができてよかったと思っています。職員は皆さん、最善を尽くしてくれました。今はもう病院への怒りはありません。ただ無力感や虚脱感でいっぱいです」
最期に「オヤノコト」®相談室がお手伝いできたのは幸いでしたが、コロナ禍という環境下では仕方ない面はあったとはいえ、大塚さんやお母さまの気持ちを思うともっとできたことがあったのではないかと無念でなりません。
みんなで考える「そろそろ親のこと、自分のこと・・・」
「オヤノコト」相談サービス(無料)
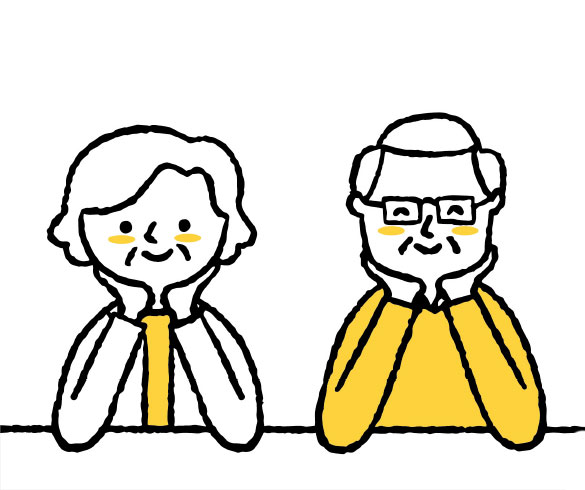
例えば、「離れて暮らしている高齢の親のことが心配」「親の住まいはどうする?」という問題を解決しようとすると、「自分の親に適したサービスは?」「お金の準備は?」「空き家になった実家はどうする?」と、次々に連動した新しいお悩みが出てくるもの。
「オヤノコト」相談サービスでは、各専門の相談員と連携しながら、『全部まとめて』相談をお受けします。出版事業で培ってきた知見とネットワークを生かし、経験豊富な相談員を揃えて皆様のお悩みに向き合います。
漠然とした不安やお困りごとからでも、ご遠慮なくご相談ください。
・介護、相続に関する相談
・離れて暮らす親の見守りの方法
・老後の住まい(ホームの相談、紹介)
・老後の資金計画(シミュレーション)
・お墓の建立、引越、墓じまいの方法
※上記以外も何でも相談できます。
調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら