「お問い合わせ」はお気軽に
親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など
「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています
体験予約・個別相談は
03-6265-0446
平日10時~18時
相談してみる
「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の
お試しのため来店を希望される場合は
原則ご予約をお願いします。
※予告なくお休みとなる場合があります。


第9回:相談者50代、対象者(義父、義母・90代、父親、母親・80代)

画像はイメージです
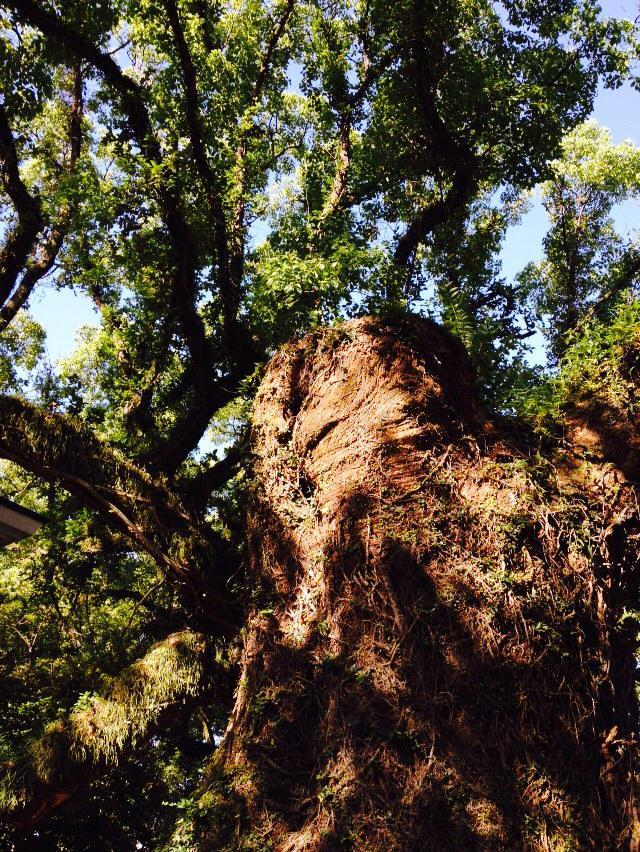
20年ほど前に親を呼び寄せ、母を看取った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて考えるように。施設やそこで暮らす親世代、認知症、高齢の親と子どもの関係、終末期に関するブックレビューなどを執筆
内野亮一さん(仮名・56)は、この数年立て続けに親を亡くしました。妻の母、父、そして実父……。遠距離介護から呼び寄せ、そして看取りと、積み重ねてきた介護経験を生かし、今は長野で一人暮らしをする認知症の母親を支えています。時にクールにも見える内野さん流の介護とは?
◆登場人物
内野亮一さんの両親
父親(80代) 長野で妻と二人暮らしをしていたが、足腰が弱って介護が必要に→地元でショートステイ施設に→東京に呼び寄せ、有料老人ホームに入居
母親 (85歳) 長野で夫の介護を担っていた→夫が東京に行き、一人暮らしに
内野さんの義父母(妻の両親)
義父(90代) 四国で妻と暮らしていたが、認知症が進行して地元の老人保健施設に入所
義母(90代) 四国で夫と暮らしていたが、夫が施設に入所したため一人暮らしに→栄養状態が悪化し東京に呼び寄せ、有料老人ホームに入居
内野亮一さんの母親(85)は、実家のある長野で一人暮らしをしています。認知症で、家族の顔や名前はわかっているものの、日時や場所がわからなくなる見当識障害があり、お金の管理も難しくなっています。
「自由に使える数万円だけ母に渡して、それ以外の金銭管理は私が行っています。母はデイサービスやヘルパー、訪問薬剤師を利用して、一人暮らしを続けることができています。私が実家に帰るのは月1回程度。金曜日は実家で在宅勤務をし、翌日には自宅に戻ります。家族との時間や自分の休日を確保したいと思っているので、このパターンに落ち着いています」
介護サービスを最大限活用して体制を整え、母親の一人暮らしをうまく回すことができているのは、父親や妻の両親の介護経験があったからだと自負しています。
内野さんは、四国に住んでいた妻の両親、長野の父親を、順次東京の内野さん宅の近くにある有料老人ホームに呼び寄せています。最初に呼び寄せたのは妻の母親(当時90)。義父(当時91)の認知症が進行し、地元で病院に併設されていた老人保健施設に入所したので、義母は一人暮らしになっていました。
「義母のために見守りシステムを利用していたのですが、義母の動きが20時間以上感知できなかったのです。運営業者が駆けつけたところ、栄養状態が相当悪化していたことがわかりました。義母は昔からあまり社交的でなく、口数も少なかったので気づかなかったのですが、以前から室内に空のペットボトルやプリンの容器がたくさんたまっていたことに思い当たりました」。
内野さん夫婦は、義母の一人暮らしは難しいと判断しました。義父と同じ施設に入所するという選択肢もありましたが、認知症の義父が義母に暴力をふるったことがあったため、二人を離した方が良いと考え、東京に呼び寄せ有料老人ホームに入居してもらうことにしました。
義母は当初は東京に行くことを嫌がっていたといいますが、内野さん夫婦が言葉を尽くして説得。義母を思う気持ちが伝わったのか、納得してくれました。
「義母はずっと宅配弁当くらいしか食べてなくて、温かい食事を摂っていなかったのでしょう。ホームの食事を『おいしい』と言って喜んでくれたのです。この言葉を聞いて、やはり東京に呼んでよかったと思いました」。
上京する際、自分で歩いて新幹線に乗れるほどしっかりしていた義母でしたが、ホームで新型コロナウイルスのクラスターが発生して感染、急逝してしまいました。コロナが猛威をふるっていた2021年のことです。どうしようもなかったとはいえ、タブレット越しの別れとなったのは、義母にとっても家族にとっても悲運でした。「コロナ禍がなければ、今も元気でいたと思います」と、無念さがにじみます。
認知症の義父は義母の死が理解できないだろうと、知らせることはしませんでした。
(第2話につづきます)
みんなで考える「そろそろ親のこと、自分のこと・・・」
「オヤノコト」相談サービス(無料)
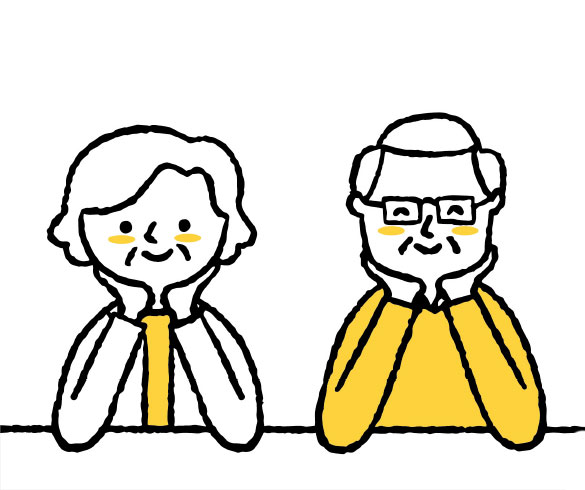
例えば、「離れて暮らしている高齢の親のことが心配」「親の住まいはどうする?」という問題を解決しようとすると、「自分の親に適したサービスは?」「お金の準備は?」「空き家になった実家はどうする?」と、次々に連動した新しいお悩みが出てくるもの。
「オヤノコト」相談サービスでは、各専門の相談員と連携しながら、『全部まとめて』相談をお受けします。出版事業で培ってきた知見とネットワークを生かし、経験豊富な相談員を揃えて皆様のお悩みに向き合います。
漠然とした不安やお困りごとからでも、ご遠慮なくご相談ください。
・介護、相続に関する相談
・離れて暮らす親の見守りの方法
・老後の住まい(ホームの相談、紹介)
・老後の資金計画(シミュレーション)
・お墓の建立、引越、墓じまいの方法
※上記以外も何でも相談できます。
調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら